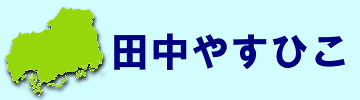


~いまの若者や中堅世代に関して感じていること~
日本の人口が減少傾向の中、各種アンケートでも日本は総じてよくない方向にあるという結果が出ています。いまの若い世代が夢を持てる地域にするにはどうすればよいか。老壮年の方々も行く末の我が国を憂い、自分の介護環境のこれ以上の整備(=将来負担)を望むよりも、最近のキレる若者・中堅世代へ今一度元気を取り戻してほしい、彼らの世代に手厚い支援が行き届いて欲しい、と願っているのではないでしょうか。
若年世代の就業環境面では、コロナ禍以前より雇用情勢悪化を通じた非正規雇用が横行し、企業は労働コストを極限まで縮減の方向にあります。それがひいては若者の晩婚化や少子化、年金・保険・納税すべてに問題を引き起こしているのです。
一方、治安維持の観点でいうと、夜中に繁華街や幹線道路でバイクの騒音を轟かせる所謂非行少年は、統計上でも反社会的勢力の入口の存在となっており、若年層のこうした集団化への誘惑を大人が毅然とした態度で断ち切る必要があると思います。「お父さん、どうして大人はこうした青少年を叱らないの?叱られないなら楽しそうだから僕も入ろうかな」、となった場合に体を張ってでも親は子供を非行集団から切り離す勇気を持てますか。早急に大人のルールを解らせる必要があるのです。
全体的に犯罪が増えた場合、冷暖房・医療対応完備の刑務所での衣食住含めた収容コストは受刑者一人当たり年間3百万円にも上り(刑務所の経済学刊)、一方で所内労働従事による家具などの成果物の販売難から、収支は当然大幅赤字になります。その原資は同じ時間に一生懸命働く県民からの税金で賄われている実態もあるのです。
~その要因・課題について思うこと~
若者・中堅世代を取り巻く背景として、2025年には団塊世代が後期高齢者になり、急速な人口減少が始まります。加えて65歳以上の高齢化率は2020年29%→2030年31%→2040年36%と増加の一途をたどります。人口は減っても高齢化率が上がり、現役世代が負担する社会福祉関連費は増える傾向にあるのです。
また、今の30代~40代はロストジェネレーション世代と呼ばれ、新卒の時期に景気循環の谷が重なった就職氷河期から正社員になれなかったものも多数存在します。彼らは入社初期の社会人教育というものを受けた経験がなく、そのまま不安定な非正規雇用を続けざるを得ない事情もあり、消費活動にも慎重になっています。
加えてアラフォー世代になると、7040問題つまり40歳の子が70歳の親の面倒を見なければならない事情も発生します。20代で親と同居していた世代も当時50代の親が現役でいる限り経済的困窮は少なかったものの、親が70代になってその介護や死去が到来すると生活は苦しくなるばかりなのです。早急に就業の機会・選択肢を提供する時期に来ています。
非行防止の観点では、共働き世帯が一般化する中、中高生のうち部活動を抜けしかも塾や習い事に通わない生徒はその時間帯に同様の者と一緒に過ごすこととなり、非行の温床になりやすいとの分析結果もあります。通信技術の向上で学校以外の集団との接触が容易に行えることも拍車をかけています。シングルマザー宅で、日中昼時に若年層がたむろする所に非行集団から執拗な誘惑が取り巻いている現状があるのです。
~解決策(政策)について~
①大人のルールの再認識(非行防止・取締り厳格化)
まず青少年が健全な社会の一員となり行政支援対象の資格を得るためには、間違っているならば正しい方向に毅然とした態度で大人のルールを分からせる必要があります。暴走行為の場合に、現行犯逮捕に拘るあまり徹底した追跡実施が負担になるのであれば、監視カメラによる当事者特定で日中の身柄拘束と違法車両没収を行うことです(没収に関しては法律上の財産権との兼ね合いも必要)。
また周囲の大人の通報機運向上を企図し、情報提供の呼びかけを強力に推し進めます。当事者の親は勿論のこと近隣住民も「この子が当事者だ」とわかっているのであり、匿名を念頭に情報をつなぎ合わせ張り巡らせた監視カメラをつないでいけばよいのです。
②就農機会の提供
若年世代の労働機会をとらえたとき、今後の全国的に必要とされる産業を考え、まずは食糧危機を打開するうえで農業へ傾注することが賢明であろうと考えます。我が国は今後、食糧危機というかつてない課題へ直面するのであり、食糧問題は県民レベルで早急に進めておく問題と考えます。域内の遊休地を若者が農業技術を学ぶ場として確保します。自然を相手に春夏秋冬作物と格闘することで1年経過したら後続の先輩に当たるのであり、技能を伝承していくことが働き甲斐に通ずると考えます。
また、非行少年の立直り支援の観点では、青少年の夕刻時間の有効活用として就農へ興味がわく仕掛けづくりを練っていきたいと考えます。こうした若者が放課後帰宅から夕食までの空白時間を空虚に過ごすのでなく、情熱を振り向ける対象として「就農」を矯正プログラムに盛り込みたいと思うのです。
農業指導は近隣老人の生き甲斐確保につながり、また次節の作物候補などの協議設定や収穫物の調理方法PRなど、若者を飽きさせない企画は行政サイド主導で汗をかきたいと思います。
③外国人材との技能交流促進
外国人実習生と若者・中堅世代の農業を通じての交流を図ることで、将来課題として、域内の若者が今後世界に打って出る体制を応援したいと思います。日本の技術を学んだ実習生たちは本国に帰ってからはその道のカリスマとなる可能性大であり、彼らの発言権が極大化した際には日本への恩返しで友好都市連携に発展し、世界の食糧危機下でも互いに収穫品融通が利く関係維持に努めたいと思います。
~まとめ~
つまり、有権者狙いの高齢者福祉偏重政策をいつまでも議論するのでなく、その負担を担う若者・中堅世代へ諸施策の重点を移すべき時期に来ているということです。いまの現役世代が介護保険・後期高齢者保険を実質的に負担しているわけですが、実際に自分がそのサービスを受けられる年齢に達したときに日本が破綻していたらどうしようもないのです。
いまの若者が不遇な時代に生まれ非正規職場で不安定にある側面は重く受け止めるべきで、ただ生まれた時代が悪かっただけで済まされるものではないのです。そこに光を当てないと将来の日本の担い手がいなくなってしまう。一部の高い教育を与えられた富裕層だけで日本が成り立っているわけではないのです。
そのための就労支援として今後必要とされる産業=農業をあげたいと思います。今後日本はエネルギーと食糧の途絶にどうしても直面して行くのであり、今後の食糧危機の回避を考えたときに就農という概念は必ず必要になります。足りない食糧を海外から調達しようにも海外諸国自体が自分のところで手一杯であるし、中国に買い負けということが常態化されたときでは遅いのです。いまのうちにこの地域で豊かな土地相手にスマート農業を確立しておく必要が急務と考えます。
人的資源確保にもつながりますが、急務の問題として反社会的勢力の入口にある非行少年(予備軍)を厳格に取り締まることを優先します。そういう時期に来ているのです。そのあとですが、補導した若者に対して矯正プログラムで就農支援をとり上げます。こうして汗をかいて世の中の役に立つ仕事があるということをまず知ってもらいたいのです。やがてプログラムから解放される時が到来しますが、興味を持ってもらえたならそのまま留まってもらっても構いません。収穫品を金銭に換算するような仕組みを作り上げます。それによって彼らはよき指導係にもなり、域内産業として農業が盛り上がってまいります。
若者の空いた時間に情熱を振り向ける対象としての農業は自然との格闘ですが、その土地や道具などのインフラについては行政支援が必要でしょう。その効果的配備については他の項目で詳述いたします。