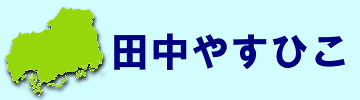


~いまの物価高騰・今後の食糧危機について感じていること~
現在の物価高騰局面において、特に食料については為替動向よりも中長期的にみて、地球温暖化に伴う気象条件の悪化や世界人口爆発などに起因する食糧危機の回避が急務と考えます。県民の皆さんがまず自分にできることは何か。入口である地産品を増やすことであり、中間過程である個包装など環境意識の向上であり、出口である食品ロスの解消など、一人一人の影響力は小さいかもしれませんが、日々の暮らしの中のちょっとした行動変化で今から取り組めるものは色々とあります。
先進国の中で最低水準である国内食料自給率を上げていくには、整った農地とその担い手が両輪ですが、農地貸借への考察では、県内データでも2030年は2020年度より生きた農地が4割減る予測にあるなか、広島市行政でも域内農地の賃借ハードルを下げて最低面積10㌃を1㌃へ小規模化し、小規模農地の活用で更なる荒廃防止を企図しているところです(農業経営基盤強化促進法により市町村が利用権限を設定可能)。ちなみに東京都練馬区では、月400円での農地貸借制度が近隣家族に好評で、いわば家庭菜園の集積化が進んでいる結果につながっています(2022年6月24日・NHK「72時間ドキュメント」)。
~その要因・課題について思うこと~
食糧危機回避の入口では、域内産品の地産地消を推し進めることが地元農家の供給力維持強化につながり、また家庭菜園の広がりなどを通じた供給力増大への県民参画などがあげられます。その一大集積地整備については別項の政策のところで述べます。
出口では食育を通じた環境学習との相乗効果追求、食育の一環としての食品ロス削減への家庭内取組み、賞味期限の慣習に左右されない消費行動などです。
~解決策(政策)について
①収穫物の有効活用による県内食糧危機回避
前述の耕作放棄地の整備からやがて経営目線を確立していくに従い、家庭菜園代わりに近隣住民にも開放し、ここでの食糧危機回避に向かってもらうことになります。まずは自家消費による域内全体の食費高騰軽減が恩恵の第一歩ですが、一大収穫地として大豆であれば代替肉開発者への売却等市場価格での販売も視野にいれてよいでしょう。まず最初の目標は域内食糧危機回避の模範例となるというものです。
ただし、行政サイドからの初期資金投入となれば、収穫物を別仕入れで販売する民間業者の経営を圧迫するので、ここはソフトランディングの議論が必要です。これらを条例で確固たるものにしていきます。民業圧迫批判の解消に向け、土地整備+建物設備は当初は行政主導で行うが、地域内が食糧危機に陥るのを回避するための必要最小限の行政補助は大義上有効と考えます。また食料販売事業者が調達サイドで支障をきたすことも今後想定されますので、ここの収穫品を優先的にその民間事業者に融通することも有用です。
地産地消強化の観点では、域外調達の弊害(物流コスト・トラック人材不足・エネルギー消費・時間経過に伴う商品鮮度ロス・荷崩れ防止の過剰包装など)に比べ、地元産品の場合の各種比較数値化の提示が環境意識の高揚につながるとともに、実際にかかった間接コストをそれがかからなかった地元産品への適正比率での利益還元ができないか、ということも検討に値します。食品ロス回避との組合せにつなげていければよいと考えます。
②学校給食無償化の永続
こうした動きがひいては給食の無償化について展開できるでしょう。各自治体で学校給食の無償化を進めていますが、今後の食料高騰を見据えた場合にその永続性を確実なものにするために、各県自治体で地産地消をもっと強化すべきと考えます。
これが流通障壁になっては本末転倒ですが、ある程度は地域内優遇も考えていく時代に来ていると考えます。優遇適用のためには、どれだけ環境面での貢献があるかなど給食提供側に達成ハードルを設け、県内産消費の達成度に応じて無償化の度合いを変えていくのであれば財政補助の大義に使えると考えます。そのためには県民参画により自らも汗をかく努力が必要でしょう。
~まとめ~
つまり、農産品の供給力強化の面で、地元農家が安心して作付けを行えるべく、ある程度売れ残り産品を行政ともにリスク分散する仕組みを作るとともに、ここに近隣住民参加も取り入れて皆で汗をかく楽しみをわかち合い、その汗かいた分だけ収穫品の恩恵に浴することになります。
加えて、食料品の購入スタイルを変化させるべくアクションを起こしたいと考えます。丁寧な個包装がもたらす環境面のデメリットや中間マージン等を総合的にとらえ、最適な商流を県民のみなさまのご理解のうえに考えてまいります。
こうした一連の動きを域内食糧危機回避につなげ、子育て世代には学校給食無料化の永続といった新たな高次元のメリット享受につなげたいと思います。各自治体で無償化を実施していても、この先全世界での食品価格高騰が不可避であり、ここを少しでも早いうちに緩和しておこうというものです。