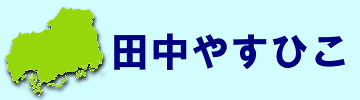


~いまの老壮年の現状について感じていること~
人生100年といわれる中、現役をリタイアして余裕ある時間の有効活用を模索している層も少なくないでしょう。資金にもゆとりがあり消費活動も旺盛であるし、これまでの優遇政策を受けて個々人が受ける社会福祉対策も充実していることでしょう。ただ、そうして自分は恵まれた時代にいると感じる一方で、今後の日本の姿を憂う方々も多数存在することと思います。通信技術の発達と符合して人をだます行為の横行、外国人犯罪を含んだ治安悪化、がむしゃらさを忘れ努力を怠り楽に稼ぐことを狙う若者の風潮、公共交通機関等ですぐにキレる現役世代など、老壮年から見た懸念材料は日本の行く末を暗澹たるものとしていると感じます。
~その要因・課題について思うこと~
核家族化の進展により祖父母と孫との接点が失われ、また母親の子供への溺愛・逆に子育ての悩みからくるネグレクトなど、子供・青少年を取り巻く環境が依然とは大きく異なってきています。昔からの日本のしきたり・礼節が薄まっていき、また年長者を敬うのでなく逆に詐欺対象とするなど、年長相手を軽く見る傾向にあるなか、伝統文化の良い面を残す伝道師的役割がいないことも、日本が悪い方向になっている要因と考えます。
一方で親の世代も青少年育成などに対し一人で悩むことも多く、互いの世代間の隔絶が今後も深刻化していくことが懸念材料となっています。
加えて、青少年同士のがむしゃらさを敬遠・蔑視する風潮から、部活動に参加しない生徒も増えており、何か打ち込める対象としての新たなテーマを考えたいと思います。
~解決策(政策)について~
①しきたり礼節文化伝承機会の確保
年初のお屠蘇から始まって年末の除夜の鐘の意味など、忘れかけている日本の年中行事の理由をいま一度思い出す場を行政エリア内に開設し、老壮年自身が互いに学びあいやがて伝道師マイスターとして展開させていきたいですね。
当初の聴講生は非行少年立直り支援の対象者、つまり行き場のない若者の有効時間活用の場として強制参加とします。これは矯正プログラムに入ります。やがてこうした活動が広まっていくに従い、近隣の放課後を有効活用したい生徒や小学生また親と幼児の組合せなど、伝承と合わせ子育ての悩み解決、つまり近隣3世代同時学習の場などを通じた、かつて美しかった日本を見直す場を創設したいと思います。
②伝統芸能を追求する部活動の県内公立高校への創部
ある程度知識材料が集積した時点で教育委員の知見も取り入れて、域内の学校に伝統文化部(仮称)なる正式な部活動としてこれを創設したいです。文化歴史を学ぶ中でその時々に存在していた諸道具などの再現工作を通じ、モノづくりと知識伝承を兼ね備えた部活動とすることも有用でしょう。候補には、琴・三味線・鼓・居合・殺陣・甲冑・着物、などがあげられます。
また、部創設であっても教職員の追加負担によるものでなく、地元有志の監督就任による各種大会での成功報酬実施なども視野にいれ、ただし部内でトラブルがあった場合の責任の所在を工夫したいと思います。多忙を極める教職員のこれ以上の負担にはさせません。
こうした活動はおそらく全国見渡しても存在しない新規性ある部活動ということになり、課外授業扱いでの域外生徒からの参加も可とします。磨いた技能の発表の場として近隣の民間商業施設・宿泊施設・介護施設等への出演依頼を受けられる体制とするのもよいでしょう。
③外部人材の出張講座開設
民業圧迫との批判回避のため、既存の各種教室からの外部講師としての招聘も検討に値すると考えます。どの教室も少子高齢化・今後の人口減を見据え生徒確保に苦慮しているのであり、逆にこうした学びの場へ出張依頼することで、無報酬ではないものの共存共栄が図れるものと思料します。
~まとめ~
つまり、現在の若者の軽薄な文化を改めるうえでも、古き良き日本のしきたり・目上を敬う姿勢・大人のルールの威厳復活をもくろみ、まずは日本・広島県内の礼節しきたりを世代間問わず再度学ぶ機会を設けたいと思います。
そのために活躍いただく方々について、まずは長年勤めた職場をリタイアし若干時間にゆとりのできた壮年世代にその先駆者となっていただき、やがて当初聴講生であった若年層に波及していくことを想定します。交流の場は行政側で整備していくこととなります。若年中堅世代の方々が加わることで、またそのお子さんを連れてくるようになることで近隣3世代の交流が深まり、壮年は文化を伝えるという役目を通じて自分のこれからの生き甲斐を見出し、中堅世代は子育ての悩みを打ち明け共有することで解決策を見出し、何よりもコロナ禍で失われた人と人との交流の復活という観点からこれを推し進めたいとも思います。すでに各地域のボランティア活動の中でこうした取組みは始まっていますが、これを県全体でバックアップしてゆこうというものです。
また、伝統芸能・伝統工芸品の再現を企図してモノづくりなどにも接していただき、その喜びを味わうとともに、良き継承者となっていただくことも視野に入れます。高等教育での部活動として広く認知していただくとともに各場面で成果発表の機会をとらえ、また伝統工芸の域内産業の再興とIT技術との融合による新産業創出振興など、『欲』はとどまりませんが、従前の政策のような新産業を外から多額の補助金で誘致するといった将来負担の残る政策とは見方を変えて取り組んでいきたいと考えます。